 【戦国大名 小野寺一族】
【戦国大名 小野寺一族】


稲庭地方を支配した小野寺氏は、下野国(栃木県)都賀郡小野寺郷(現栃木市岩舟町小野寺)の出身。鎌倉時代に入り、戦のほうびとして源頼朝から雄勝郡を賜った。
小野寺氏が最も繁栄した時代は、小野寺泰道(やすみち)、輝道(てるみち)、景道(かげみち)の三代の時代であった。その城館(じょうかん)は、仙北に157城、平鹿に174城、雄勝に93城。その他、由利の一部や山形の一部支配下にあったものを数えれば470もあったといわれている。
稲川町(現湯沢市稲川地域)には、三又城、大館、八幡館(はちまんだて)、牛形城、三梨城、川連城、新城館、稲庭城などがあり、一村一城館で治めていた。
特に稲庭城は稲庭系小野寺氏の本拠地であった。
天正10年(1582)には支配領域は雄勝・平鹿、仙北・由利地方にまでおよぶ戦国大名に成長した。
しかし、領地が拡大したため隣り合う領主と戦いをくり返し、次第に勢力は弱まっていった。
天正19年(1591)に秀吉の検地の結果、石高が2/3に減らされたうえ、慶長5年(1600)山形の最上義光(よしあき)の総攻撃を受けて敗退。さらに翌年の関ヶ原の戦で上杉氏へ味方したという疑いによって、城や領地がすべて取り上げられてしまった。

関ヶ原合戦後(慶長6年・1601)は、石見(いわみ)国津和野(島根県)にお預けの身になったと言われている。
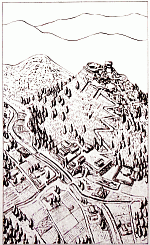
|
【稲庭城 復元想像図】
山上には、戦争になったとき立てこもる山城があり、その麓に根小屋と呼ばれる住まいがあった。山城のつくりは簡単で、最も高い所に櫓(やぐら)が立っている。下の段に開けられた木戸のわきに竪堀が、それをへだてて横矢がかりがある。 ここからジグザグの坂道で根小屋に下りることができる。こちらは日常生活する建物なので、つくりも立派で、まわりに櫓や門前に堀をつくり土橋を設けている。
|
|