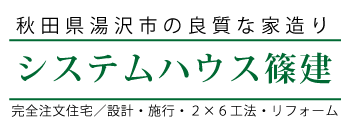家造りには、建物本体の工事以外にかかる費用があります。
物に付帯する工事、各種税金、借入にかかる費用、登記費用などです。
全体の予算をしっかり把握して綿密な資金計画を立てましょう。
新築の場合、建替えの場合と、それぞれ費用は変わってきます。
住宅建築には、どのくらいの費用が必要なのかをしっかり把握しておきましょう。
※下記内容は2017.10.2現在の情報です。
①付帯工事費 建物に付帯する工事費用
外構工事
建物本体以外の外部廻りの工事です。
建物廻りの土間コンクリート、雨水側溝、花壇、植栽、塀工事など
給水引工事
道路に埋設されている水道管から建物の敷地内に水道管を引き込む工事のことです。
※宅地内に水道管がない場合に費用がかかります。
電気引込工事
電柱から建物内に電気を送る工事のことです。
建物へ直受けできない場合は別途引込ポール等の費用がかかります。
既存建物解体工事
建替えなどの際に、既存の建物を解体するための工事です。
地盤改良工事
敷地の地盤調査を行った結果、地盤改良が必要になった宅地に行う工事です。
建物をしっかり支持できる地盤するために必要な工事です。
浄化槽設置工事
家庭の排水(し尿)や台所・洗濯・風呂などからの生活排水を微生物の働きを利用して処理し、きれいな水にして河川に放流します。そのための個別に設置される設備を工事します。
一部助成金有り ※下水道埋没地域は除く
車庫・カーポート設置工事
必要な場合は車庫やカーポートの工事があります。
②諸費用 各種税金、借入の諸費用、登記費用など
印紙税
各種の契約書を取り交わす際には、記載された契約金額(借入金額)に応じて印紙税がかかります。
「建築工事請負契約書」「不動産売買契約書」「金銭消費賃借契約書」など
消費税
消費税は建築金額または建物価格の8%です。土地については非課税です。
※要注意 一般的に坪単価は含みません
登録免許税
保存登記(新築)、所有権移転登記(土地・中古住宅など)や抵当権設定登記を行う際には、固定資産課税坪価額・借入額に応じて、登録免許税がかかります。
建替えの場合には「滅失登記」が必要になります。
不動産取得税
土地や建物などは取得したときにかかる税金です。
不動産取得後60日以内に申告すれば、条件により軽減措置が受けられます。
住宅関係 土地 3% 平成30年3月31日まで
建物 3% 〃
住宅以外(店舗・事務所等)土地 3% 平成30年3月31日まで
建物 4% 〃
日付が30年なので、情報を新しくした方がいい???
■新築住宅の不動産取得税の計算方法 (軽減措置)
| 新築住宅値額 - 1,200万円 (固定資産税評価額) | ×3% | =税額 |
[摘要要件] 床面積50㎡以上240㎡以下であること。
■土地の不動産取得税の計算方法
一般の住宅用地は固定資産税評価額の2分の1に対して課税されますが、下記の適用要件のいずれかに該当する新築住宅の土地については、その税額からさらに減額される特例があります。
〔特例の適用要件〕
●土地を取得してから3年以内に特例適用住宅(軽減の条件を満たす住宅)を新築または、取得する場合
●土地を取得してから1年以内に未使用の特例適用新築住宅を自己の居住用に取得する場合
●未使用の特例適用新築住宅および敷地を新築の日から1年以内に取得する場合
●特例適用住宅を新築してから1年以内にその敷地を取得する場合
| 一般の住宅用地の税額 | 特例適用住宅酔用地の軽減額 |
| [ 宅地の固定資産税評価額 × 1/2 ] | ×3% | A 45,000円 B 土地1㎡あたりの評価額×1/2 ×住宅の延床面積※×2×3% (AとBのどちらか多い方) ※1戸につき200㎡まで | = | 税額 |
◆住宅ローン(融資)に必要な費用
一般的に、金融機関の住宅ローンを利用すると以下の費用が必要になります。
- 金銭消費貸借契約書に貼る印紙代
- 融資機関に支払う融資手数料
- 保証会社に支払うローン保証料
- 保険会社に支払う団体信用生命保険料 (融資機関により金利に含める場合有)
- 火災保険料と地震保険料
- 抵当権設定登記 (登録免許税+司法書士への報酬)
- つなぎ融資利息(住宅ローン実行までの一時金利息)
◆表題登記費用・家屋調査士費用
建物表題登記がなされると、不動産登記簿に表題部が設けられ、建物の所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積などが記載されます。
◆保存登記費用・司法書士費用
所有権保存登記がなされると、不動産登記簿の権利部甲区に、その建物の所有者は誰で、いつ、どんな原因で所有権を取得したのかなどが記載されます。
建物表題登記が完了した後に,自分が建物の所有者であることを示す登記を申請いたします。
◆抵当権設定登記費用・司法書士費用
所有権保存登記がなされると、抵当権設定登記をすることができます。抵当権設定登記は、不動産登記簿の権利部乙区に記載されます。
住宅ローンを借りて建てる家など(不動産)に抵当権を設定するための登記です。
◆建物滅失登記費用・家屋調査士費用
建物、家屋を解体したら1ヶ月以内に建物滅失登記を行わなければなりません。(不動産登記法57条)
法務局の登記簿上からその建物が存在しなくなったことを登記しなければならないのです。
◆各種負担金など
家を建てる地域や条件によって異なりますが、以下のような負担金があります。
給水負担金、放流負担金…上下水道の利用にあたり、水道局等に納付します。
その他の諸経費
建て替えの仮住まい費用や新築に備えて家電や家具などを購入する費用なども、必要な場合は経費として考えておきましょう。
家造りをスタートする前に、必要な費用の内訳をしっかり把握して
予算オーバーを防ぎましょう!