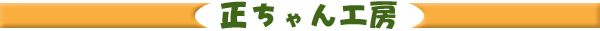
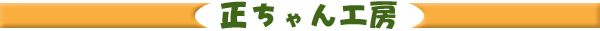
| 雄勝福祉会の発明王、菅正地域福祉センター長(デイサービスセンターなるせ管理者)の手作りグッズの紹介コーナーです。ドラえもんのポケットから色んなものが出てくるように、センター長のドラえもんのような大きくかつ可愛い手からは、様々な作品が生まれています。 |
| 正ちゃん工房に看板が… | |
 |
 |
| あるお宅が新築され、その時はじかれたケヤキの板をいただきました。 筆者は兄です。 |
|
| 「なるせ」の看板 |  |
||
東成瀬村の習字の先生に書いていただきました。 |
|||
 |
『物干し No.1』 | ||
畑作に使用されているイボ竹を利用し作成したもの。 |
|||
| 『物干し No.2』 |  |
||
No.1は隙間が少ないとの意見から、このような形になりました。 |
|||
『体重計』 |
|||
| 車いす専用の体重計は市販されていますが、「ヘルスメーターを使用し測定できないだろうか?」との思いから生まれました。 | |||
 |
 |
||
 |
『クイックオセロ』 | ||
正規のオセロは20分ほどかかりますが、一回り少なくすることで駒数も約半分となり、勝負が早くなります。 |
|||
| 『歯ブラシ整理台』 |  |
||
村の歯科医師の指導を受け、昼食後みんなで歯磨きを行っています。自分の歯ブラシは一目で発見できるようになりました。 |
|||
 |
『髭剃り整理台』 | ||
「盾(たて)ですか?」と言われました。ホテルでは使い捨てかもしれませんが、まだ剃れるのにもったいない。名前をつけ保管しておくと、数回使用することができます。安価で感染予防にもグット! |
|||
| 『円卓』 |  |
||
直径150センチの電線を巻く使用済みドラムを積んだ車が「なるせ」の駐車場に入ってきました。 無理を言って頂き、作成しました。K電工さんありがとうございました。 |
|||
 |
ダイヤフラムを使用した 『ナースコールスイッチ』 |
||
車のクラクション、弁当箱などを組み合わせて作ったスイッチ。ストローを通し空気を送り、コールできる。 そんな話を聞きつけ、ある施設の管理者から「作ってくれ」との依頼がありました。 |
|||
| 『牽引シート』 (消火活動を容易にする装置) |
 |
||
水路は整備され、流速が早く水深が浅くなっていて、吸水が思うようにできませんでした。 シートを側溝に投げ込み‘よどみ’を発生させ、消防ポンプの吸引を容易にします。 |
|||
 |
『消防ホース一本巻き』 | ||
立ったままホースを巻き取る装置です。 |
|||
| 『消防ホース二重巻き』 |  |
||
ガイドを両側に取り付け、直線にしたまま巻きつけていきます。3人で作業を行うことになりますが、短時間で終えることができます。 |
|||
| 『サイコロカッター』 スノーダンプの大きさに切って行うと運びやすい。 |
|||
 |
 |
 |
|
 |
『パラレルロール』 | |
使用済みマルチを規定されたサイズに巻きつける装置です。 |
||
| ◎ぱあとなあ就労支援から生まれた装置 | ||
| 『ポリパック二重折装置』 | ||
| 片麻痺の方が、ビンにポリパックを被せ外側に折っておりました。しかし、内側に折ることが要求されておりました。そこで、ステンレス製の針金を楕円形にし、固定のための脚を取り付けます。これに、右側からポリパックを差込み縦にします。その後、上側から押し込み二重にします。そして、左側の上部をつかみ右側に抜き取ります。 | ||
 |
 |
 |
 |
 |
| 『ポリパック整理箱』 |  |
二重に折ったポリパックを20個ずつ整列させておく箱です。このようにすることにより袋詰の時間短縮を図ることができました。ダンボールで作ったものが軽量で皆さんに好まれるようです。 |
|
 |
『ポリパック梱包装置』 |
定められた袋に20個ずつ5段に詰める作業ですが、形が変形する袋に詰めるのはクラッシュすることも度々ありました。そこで写真のような箱にビニール袋を押し込むことにより、クラッシュすることも少なくなりました。 |
|
| 『ローラー文鎮』 |  |
タオルをたたむ作業を受注しましたが、片麻痺の方がタオルを広げるには時間がかかります。そこで、片側を一直線にし、そこにローラー文鎮を転がし乗っけます。そして反対側を広げます。文鎮をよせ、中央に竹棒を差し込み持ち上げ、二重折りにしてテーブルに広げます。この作業を繰り返し作業は完了となります。 |
|
 |
『F君からの依頼…』 (F君の設計図を基に制作した装置) |
この作業は、フイルムの中に挟まれている品物を抜き取る作業ですが、F君が自分でも行いたいと設計図を書いてきました。それを基に制作したものです。 彼は足のみで行い、不要な品物を発見したところで他の人が取り出すという作業分担で行っておりました。 |
|
||||||||||
| 2ページ目へ |