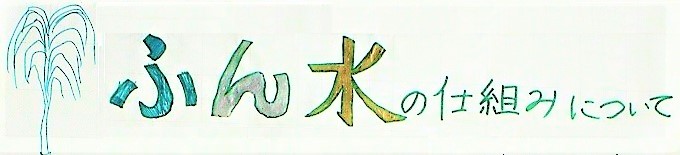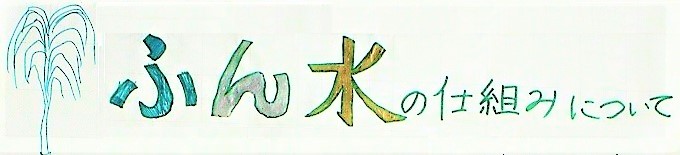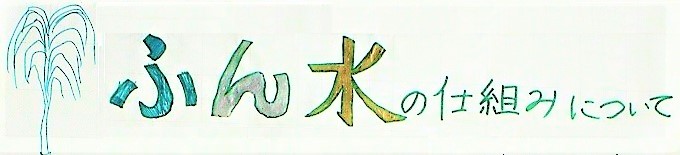
西馬音内小学校4年 スタンリー
- 1.動機
-
gyakusaifon.jpg) 去年のテーマ「コップの中の水を出すいろいろな方法」で、サイフォンの原理について調べたとき、逆サイフォンの原理が日本庭園のけん六園のふん水に利用されていることを知ったからです。
去年のテーマ「コップの中の水を出すいろいろな方法」で、サイフォンの原理について調べたとき、逆サイフォンの原理が日本庭園のけん六園のふん水に利用されていることを知ったからです。
- 2.調べたこと
-
- (1)水だけで動力を使わないふん水装置を作ること。
- (2)ふん水になるときのしくみ。
- 3.実験その1「逆サイフォンの原理を使ったふん水」
-
-
(1)装置
- 図1のような「逆サイフォンの原理」を使った装置を作って実験してみました。入れ物のそこにビニールホースをつけて、Aの水面とBのホースの出口の高さをかえて、水の出てくる様子を調べてみました。
- (2)予想
gyakusaifon2.jpg)
- Aの水面よりも、Bのホースの出口が低い 図1ときに、一番高く上がるふん水ができる。
- (3)AとBの位置をそれぞれ変えて実験
| AとBの位置 | 水の出てくる様子 |
| AよりBが上 | 水は出口まで上がらない |
| AとBが同じ高さ | 水は出口まで来ているが出ない |
AよりBが下
(a):少し下
(b):(a)よりさらに下
|
ふん水になった
(a)ふん水が5cmくらい上がる
(b)ふん水が10cmくらい上がる
|
- (4)結果
- Aの水面よりも、Bの出口を下げれば下げるほど、ふん水の高さが高くなっていくことがわかりました。
- 4.実験その2「ヘロンのふん水」
-
- (1)装置
heron.jpg)
- 図3のように、3つのペットボトルを組み合わせて「ヘロンのふん水」を作りました。
(A)のペットボトル
左がわのストローの先が出るように水を入れる。
(B)のペットボトル
右がわのストローの先が出るように水を入れる。
(C)のペットボトル
左がわのストローを短くする。
- (2)予想
- (A)のペットボトルの水を多く入れると、ふん水ができる。
- (3)(A)を一番上にして、(B)(C)の位置を変えて実験
| BとCの位置 | 水の出てくる様子 |
| 1.BがCと同じ高さ | 水は出ない |
| 2.BがCよりずっと上 | ふん水になった |
| 3.BがCより少し上 | 少し水が出た |
| 4.BがCより下 | 水が出ない |
- (4)結果
- (C)よりも(B)が高いとふん水になった。
- 5.まとめ
- 「逆サイフォンの原理を使ったふん水」の実験と「ヘロンのふん水」の実験の両方から、「水が落ちるときの高さのちがいがあればあるほど、水の流れのいきおいが強くなっている。」と思いました。
- 6.感想と課題
-
「ヘロンのふん水」のホースの長さは関係がないのかなと、ぎ問に思った。それはキャップにホースをつけるとき空気をもれないようにするのが大変だったので、ホースの長さまで変えた実験ができませんでした。だからホースの長さはそのままにして、高さを変えた実験だけになってしまいました。
|